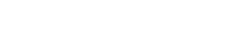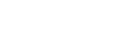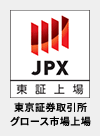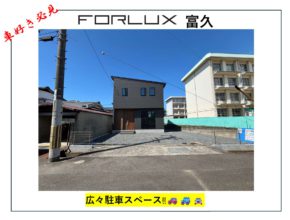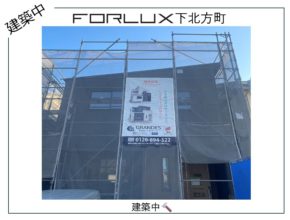更新情報
-

2025.12.13
【宮崎営業所】フォレクス本郷南方3 建築状況👨🔧
-

2025.12.11
【松山市】新空港通へのアクセス良好✈◎
-

2025.12.08
【新着情報】フォレクス藤原7登場!
-

2025.12.06
【宮崎営業所】フォレクス曽師町 建築状況👨🔧
-

2025.12.01
【大分市岩田町】建築・販売中!!
-

2025.11.29
【宮崎営業所】フォレクス曽師町 建築状況👷♂️
-

2025.11.27
【松山市】車好き必見!! 広々駐車スペース🚙
-

2025.11.24
【大分本店】大分市片島 最新情報!
-

2025.11.22
【宮崎営業所】フォレクス下北方の建築状況🛠️
-

2025.11.17
【宮崎営業所】フォレクス本郷南方3の建築状況👷♂️
-

2025.11.17
【日出町仁王】残すは外構工事のみ!
-

2025.11.13
【松山市】毎日のお買い物が楽ちん♪
-

2025.11.10
【大分】✨今期最終見学会✨
-

2025.11.09
【宮崎営業所】フォレクス大島町2 完成見学会 開催!!
-

2025.11.06
【松山市】まだ間に合う!!プレゼントキャンペーン✨
-

2025.11.02
【宮崎営業所】新着情報✨本郷南方に限定1棟販売🏠